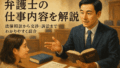「顧問税理士の費用って、何を基準に決まるの?」「本当にこの金額が適正なのか不安…」と感じていませんか。
実は、法人の場合、顧問税理士の【月額顧問料】は全国平均で約2万円~5万円、決算申告料は8万円~25万円が一般的。ただし、売上規模や従業員数、税理士の訪問頻度など「6つの要因」により、費用には想像以上の差が生じます。
また、個人事業主向けだと月額顧問料の平均は1万円前後、決算申告料は3万円~7万円ほど。記帳代行や節税診断などのオプションを追加すると、年間コストが大きく変動することも少なくありません。
「具体的な内訳や契約形態が分かりにくい…」というお悩みを持つ方も多く見受けられます。
適正価格で信頼できる税理士と契約するには、『相場』と『料金構造』の“見える化”が不可欠です。
最後までお読みいただくと、2025年最新データに基づいた料金相場と失敗しない選び方・比較基準までわかり、損をしない判断軸が手に入ります。
あなたの悩みや不安を、この記事で一緒に解決していきましょう。
顧問税理士の相場とは?法人・個人別の基礎知識と費用感の全体像
顧問税理士とは?契約形態と主なサービス内容
顧問税理士は、企業や個人事業主が会計・税務の専門知識を活用するために契約する税理士です。主に月次の会計処理や税務申告、相談対応、経営アドバイスを提供します。契約形態は「月額顧問契約」が一般的で、年1回の決算申告料を別途支払うケースや、スポット契約として確定申告のみを依頼する例も増えています。
主なサービス内容には以下が含まれます。
- 会計・税務書類の作成やチェック
- 記帳代行や経理フロー改善の提案
- 節税や税務調査の対応
- 資金繰りや経営に関するアドバイス
- 税制改正への迅速な対応と情報提供
税理士がどこまで対応してくれるかは契約内容によるため、依頼前の確認が大切です。
法人と個人事業主で異なる料金体系と相場の特徴
顧問税理士の相場は、法人と個人事業主で大きく異なります。法人は会計処理や税務対応が複雑なため、多くの場合、個人より高額な設定です。個人事業主の場合は、業務量が少なめなことや毎月の訪問が不要な場合も多いため、料金が抑えられる傾向にあります。
両者の主な相場目安をテーブルで比較します。
| 種別 | 月額顧問料の目安 | 年間決算料の目安 | サービス内容の例 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 20,000~50,000円 | 100,000~200,000円 | 月次試算表作成、決算・申告業務等 |
| 個人事業主 | 10,000~30,000円 | 50,000~150,000円 | 確定申告、経理・記帳相談、節税提案等 |
税理士に「丸投げ」や記帳代行を依頼する場合は、別途費用が発生することもあります。
最新の税理士顧問料平均額とその背景(2025年版)
2025年の最新税理士顧問料は、企業の年商規模や業務範囲、地域による違いがより顕著になっています。クラウド会計ソフト(freeeなど)の普及やオンライン対応の増加により、首都圏を中心に相場が緩やかに下がる傾向もみられます。
- 法人の顧問料平均:月額30,000~40,000円、決算料は約150,000円前後
- 個人事業主の顧問料平均:月額15,000~25,000円、確定申告料は約80,000円前後
料金が安価な税理士には「サービス範囲が限定的」「追加オプション料が発生しやすい」など注意点もあるため、検討の際は内訳や対応範囲を必ず確認しましょう。
顧問税理士費用の算出方法と料金構造の理解
費用は主に「月額顧問料 × 12カ月 + 年間決算料や申告料」で構成されます。以下の表は一般的な料金構造の内訳です。
| 項目 | 主な内容 | 支払い目安 |
|---|---|---|
| 月額顧問料 | 毎月の会計・税務サポート | 10,000~50,000円/月 |
| 決算・申告料 | 決算申告や確定申告 | 50,000~200,000円/年 |
| 記帳代行料 | 伝票入力・帳簿作成支援 | 5,000~30,000円/月 |
| オプション料金 | 税務調査立会い等 | 個別見積 |
業務量(仕訳数や売上高)、訪問回数、必要なオプションで料金は変動します。複数社から見積もりを取り、サービス範囲やサポート体制を比較して選ぶことが失敗しないポイントです。
ニーズに応じた最適な顧問税理士選びがコストの最適化と経営の効率化につながります。
顧問税理士の料金が変動する6つの主要要因詳細解説
顧問税理士の料金はさまざまな要素で変動します。ここでは6つの主要な要因ごとに、その仕組みや料金差のポイントをわかりやすく紹介します。自社に最適な費用感を把握し、賢い契約につなげるための基礎知識としてご活用ください。
売上規模・年商別の料金相場への影響
顧問税理士の相場は、会社や個人事業主の売上規模によって大きく異なります。一般的に、売上(年商)が大きくなるほど経理データや取引量も増え、必要な業務量も多くなります。そのため顧問料は段階的に高く設定されています。
下記のテーブルは、売上ごとに想定される月額顧問料の目安です。
| 年商規模 | 月額顧問料の目安 |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 10,000~20,000円 |
| 3,000万円程度 | 15,000~30,000円 |
| 5,000万円〜1億円未満 | 20,000~40,000円 |
| 1億円以上 | 30,000円以上 |
年商3,000万円を超える場合は決算・申告業務も複雑になり、年間報酬も増制されやすくなります。
従業員数・会社規模がもたらす費用への影響
従業員数や会社規模が大きくなるほど仕訳数や処理量が増加し、給与計算や労務関連業務も発生します。そのため、従業員ゼロ〜数名の小規模経営者と、数十人規模の会社とでは料金設定に大きな差が出ます。
主な影響点は以下のとおりです。
- 従業員10人未満:最安値帯での契約も可能
- 10~30人:月額2万~4万円が中心
- 30人以上:月額4万円~、業務内容やデータ量に応じて個別見積り
小規模のうちは割安なプランも多いですが、拡大に伴い顧問税理士のサポートも高額化する傾向です。
税理士訪問頻度・面談回数による顧問料の増減
税理士の訪問頻度が高いほど人件費や移動コスト、打ち合わせ時間が必要になり料金に反映されます。多くの場合、毎月訪問プランと四半期や半年ごとの訪問では費用が大きく異なります。
- 訪問なし(オンライン対応のみ):最安値
- 隔月訪問:+5,000円程度が目安
- 毎月訪問:+10,000円以上になることも
経営にアドバイスがほしい、税制改正の情報を得たい場合は定期訪問が安心ですが、クラウド会計やITツールを活用し訪問頻度を減らすことでコストを抑える方法も広がっています。
業務内容の難易度・緊急対応が料金に与える影響
基本的な記帳や決算書作成のみか、複雑な税務調査や節税スキーム相談まで含むかによって料金は大きく異なります。特に相続税や贈与税、会社設立後の税務戦略、融資対策を依頼する場合は、専門性の高さを反映し追加料金が発生します。
- 基本業務のみ:標準相場
- 緊急対応・税務調査立ち合い:顧問料の2〜3倍が目安
専門的サポートを受ける場合は内容ごとの費用内訳を事前に確認しましょう。
オプションサービス(記帳代行・節税診断等)の費用差
標準的な顧問料には記帳代行や年末調整、給与計算が含まれないことが多めです。オプション追加で費用が増減する点に注意しましょう。
| オプションサービス | 追加月額目安 |
|---|---|
| 記帳代行 | 5,000~20,000円 |
| 給与計算 | 3,000~10,000円 |
| 節税診断・アドバイス | 10,000円前後 |
サービス範囲は顧問契約時に詳細を確認し、不要なものは削除・必要に応じてスポット対応することでコストコントロールがしやすくなります。
地域差・都市部と地方の価格差
都市部と地方では税理士の費用相場も異なります。一般的に都市部の方が料金は高めに設定されがちで、最大2割程度の差が見られることもあります。
- 東京都心や大阪市内:全体的に高値傾向
- 地方都市や郊外:月額1万円前後から契約可能なケースも
対面のやり取りが少なくなった今、オンライン専門の事務所を活用すれば、地域格差による料金高騰を避けることも可能です。自社の所在地や業態に合わせ、最適なプランを選択することが重要です。
顧問税理士の相場を詳しく比較|法人・個人・依頼内容別具体料金一覧
法人向け顧問料・決算申告料の相場一覧表
法人が顧問税理士に依頼する場合の相場は、企業の規模や依頼範囲によって変動します。以下の表は、主な料金相場と内容をまとめたものです。
| 企業規模 | 顧問料(月額) | 決算申告料 | 主な依頼内容 |
|---|---|---|---|
| 小規模法人 | 15,000〜30,000円 | 100,000〜200,000円 | 記帳、申告、税務相談、年末調整、経営アドバイス |
| 中規模法人 | 30,000〜50,000円 | 150,000〜300,000円 | 会計チェック、税務調査立会、資金繰りサポート |
| 大規模法人 | 50,000円以上 | 300,000円以上 | 監査業務、経営戦略支援、専門税務対応 |
多くの場合、月額顧問料と決算申告料は別々に発生し、訪問頻度や追加サービスによって増減します。業種や所在地による相場の違いにも注意が必要です。
個人事業主・フリーランス向け料金目安
個人事業主やフリーランスが税理士に依頼する場合は、法人に比べて相場が手頃です。ただし、記帳代行や申告内容によって変わります。
- 顧問料(月額):10,000〜20,000円程度
- 確定申告代行料(スポット):30,000〜60,000円
- 丸投げ(記帳~申告すべて):50,000〜100,000円
会社設立直後や売上が少ない場合は、スポット利用でコストを抑えたい方も多く見られます。報酬は規模だけでなく、発生する仕訳数やオプションの追加有無で変わることもポイントです。
スポット契約・丸投げ依頼の料金比較
スポット契約は「確定申告だけ」「相談だけ」など単発の依頼です。一方、丸投げ依頼は面倒な経理や記帳も含め、全工程をまるごと代行してもらうものです。
| 依頼内容 | 料金相場 | 主な利用シーン |
|---|---|---|
| スポット相談 | 5,000〜15,000円/回 | 税務相談、単発指導 |
| 決算・確定申告のみ | 30,000〜60,000円 | 個人事業主の申告など |
| 丸投げ依頼 | 50,000〜150,000円 | 記帳から申告全て任せたい |
スポット利用は「税理士にいらない」と感じている方にもおすすめですが、頻繁な対応や税務調査まで含める場合は顧問契約の方がコストパフォーマンスがよい場合が多いです。
業種別(医療、士業、ITなど)顧問料の特徴と注意点
業種によっても顧問料の相場や依頼内容は大きく異なります。特に医療・士業・IT関連は専門知識が必要なケースが多いです。
- 医療・歯科業界:複雑な医療会計やレセプト処理が必要なため、相場はやや高め(月額30,000円~)。
- 士業(弁護士、社会保険労務士など):報酬体系が特殊なため、標準より高い顧問料になることが多いです。
- IT・スタートアップ:クラウド会計やfreee対応税理士を選ぶと効率的で、比較的安価(月額10,000円~)なサービスも増えています。
業種特化の税理士は、業界ごとの節税や助成金知識が豊富なため、費用だけでなく担当者の実績も比較材料にすると安心です。規模・業種に適した税理士選びを心がけましょう。
税理士との顧問契約形態と費用体系|契約の種類と注意点
定期契約とスポット契約の違いとそれぞれの費用感
税理士に依頼する際、主な契約形態は「定期契約」と「スポット契約」の2つです。定期契約では、毎月の会計や税務サポートを受けることができ、法人・個人事業主問わず広く採用されています。一方、スポット契約は決算や確定申告など単発のタイミングで税理士に依頼する形式です。両者の費用相場は以下の通りです。
| 契約形態 | 法人の相場(月額/1回) | 個人事業主の相場(月額/1回) | 主な利用場面 |
|---|---|---|---|
| 定期契約 | 20,000~50,000円 | 10,000~30,000円 | 毎月決算・税務対応、経営サポート等 |
| スポット契約 | 50,000~200,000円 | 30,000~100,000円 | 確定申告、年末調整、税務調査対応等 |
企業や事業内容、依頼する業務範囲で変動しますが、定期契約は年間費用を予測しやすい点がメリットです。スポット契約は税理士との関与が少なく、費用も都度精算される特徴があります。
顧問料の内訳とオプション料金の具体例
顧問料は基本業務に加えて追加サービスの有無で構成されます。基本の顧問料には、会計帳簿のチェック、税務相談、経営アドバイスなどが含まれますが、記帳代行や給与計算、節税対策などはオプションとして別途費用が発生する場合があります。
| 項目 | 月額または1回あたりの相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 記帳代行 | 5,000~30,000円 | ボリューム・内容で増減 |
| 決算申告料 | 80,000~250,000円 | 決算作成・申告書作成 |
| 年末調整 | 20,000~50,000円 | 従業員数によって変動 |
| 税務調査立会 | 50,000円~ | 時間単価・対応内容による |
必要なサービス内容や自社会計体制に応じて、オプションの要否を事前に整理しておくことで、予算コントロールにもつながります。税理士費用は「基本顧問料+オプション料金」という考え方を押さえておくと安心です。
契約時の注意点・確認すべきポイント詳細
顧問契約時は費用だけでなく、サポート内容やレスポンスの速さなども必ず確認しましょう。契約前にチェックすべきポイントを以下にまとめます。
- 業務範囲とサービス内容が明確か
- 見積書や料金表の内訳が詳細に提示されているか
- オプションや追加料金の発生条件が分かりやすいか
- 解約や契約期間、更新条件が明記されているか
- 担当税理士の経験や専門分野が自社に合うか確認
価格のみならず、サービス品質や税理士との相性も重視することが、後悔しない契約のための大切なポイントとなります。また、複数の事務所から見積もりを取ることで、適正な顧問料の相場を把握しやすくなります。
安い税理士・格安顧問料の裏側|メリットとデメリットを徹底解析
格安税理士のサービス内容と向いている利用者
税理士の顧問料が月額5,000円〜など、格安プランをうたう税理士事務所が増加しています。こうした格安税理士は、主なサービス内容を「会計ソフトへの自動連携やデータ入力サポート」「記帳代行」「確定申告や年末調整のスポット対応」に絞る傾向です。経営や節税に対する助言が限定的で、訪問や電話相談の回数も制限されている場合が多く見られます。
このため、個人事業主で日々の会計処理を自分で行っており、税務申告や記帳代行だけをアウトソースしたい方、コスト重視で最低限の税務サポートを求める小規模法人に向いています。下記はサービス内容の一例です。
| サービス内容 | 格安税理士 | 一般的な税理士 |
|---|---|---|
| 記帳代行 | ○ | ○ |
| 会計ソフト連携 | ○ | △ |
| 相談対応 | △ | ○ |
| 税務調査立会い | △~× | ○ |
| 節税アドバイス | △~× | ○ |
| 訪問サポート | × | ○ |
安さに潜むリスクと事前に確認すべき注意点
格安顧問料にはいくつかの注意点があります。まず、1人の税理士が大量のクライアントを抱えがちで、きめ細やかな個別対応が難しいケースが見受けられます。また、安価なプランほどサービス範囲が限定されやすく、契約外の業務に追加費用が発生する場合も少なくありません。
特に個人事業主や小規模法人では「急な税務調査対応」「複雑な税務相談」「経営アドバイス」など、想定外のサポートが必要になる場面があります。格安税理士と契約する場合は以下のポイントを必ず確認しましょう。
- 月額・年間費用以外の追加料金は何か
- サービス範囲と顧問契約で含まれる内容
- 記帳や申告業務の責任範囲
- サポート窓口や問い合わせ対応の体制
特に税理士報酬の料金表や契約書は、細部まで目を通し不明点は必ず事前に相談することが大切です。
質の高い税理士との違いと品質比較のポイント
格安税理士と質の高い税理士との大きな違いは、コミュニケーションや提案力、対応の柔軟性に表れます。経験豊富な税理士は、単なる記帳や申告業務だけでなく、経営の方向性や資金繰り、節税対策にまで踏み込んだ多面的なサポートを提供します。法人ごとの業務内容や業界特性、年商規模に応じ、最適なサービスを設計できるのが強みです。相場表を参考に比較しましょう。
| 比較ポイント | 格安税理士 | 質の高い税理士 |
|---|---|---|
| 料金のわかりやすさ | ◎(明確) | ○ |
| サービス範囲 | △(限定的) | ◎(広範囲) |
| 個別アドバイス | △ | ◎ |
| スポット対応 | ○(追加料金多い) | ◎(柔軟に対応) |
| サポート体制 | △(メール中心) | ◎(訪問・電話可) |
税理士選びでは単に価格で決めるのではなく、何を重視するかによって慎重に比較検討することが重要です。費用だけでなく、長期的な経営サポートや信頼性、トラブル時の迅速な対応力も視野に入れ、本当に自社の成長に寄与するパートナーを選ぶよう心がけましょう。
顧問税理士の選び方|料金以外で失敗しないために注目すべきポイント
顧問料が相場以上の税理士の特徴と選ぶべきユーザー像
顧問税理士の中には相場より高い料金設定の事務所もありますが、価格だけを基準に選ぶのはおすすめできません。相場以上の税理士は、以下のような点で高い価値を提供できる傾向があります。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 業界特化の専門知識 | 医療・不動産・IT業界など、特定の分野に精通し複雑な会計業務も対応 |
| 経営サポート力 | 単なる税務処理だけでなく財務分析や資金調達アドバイスも可能 |
| 税務調査・訴訟対応 | 税務調査への豊富な対応実績、リスクに強い体制 |
| 最新IT対応 | クラウド会計や効率化ツールの導入支援が得意 |
| サポートの充実 | 定期面談やスピード対応、個別アドバイスが迅速 |
こうした事務所は、成長志向の会社や複雑な税務対応が求められる法人、経営判断をサポートしてほしい経営者などに向いています。顧問料の高さだけでなく、こうした付加価値やサービス品質も含めて選ぶのが重要です。
相場以下の価格帯でのサービス内容と利用時の注意
相場よりも安価な顧問税理士は、経費を抑えたい個人事業主や小規模法人にとって魅力的な選択肢です。しかし、格安事務所のサービス内容や注意点を理解した上で選ぶことが大切です。
- 月額顧問料が安い場合の主な特徴
- 記帳代行や相談回数などサービス範囲が限定されることが多い
- オンライン対応のみ、訪問や対面相談は別料金となるケース
- 担当税理士1人あたりの顧客数が多く、個別対応の手厚さに限界
- 利用時の注意点
- 決算申告や節税アドバイスは別料金になっていないか確認が必要
- 追加費用が発生する場面(税務調査時、複雑な案件など)を事前に把握
- サービス範囲や対応スピード、担当者の経験・実績を明確にしておく
低価格でも条件によっては十分なサービスを受けられる場合もありますが、自身の事業規模や必要なサポート内容に応じてベストな選択をしましょう。
費用対効果で選ぶ税理士の比較方法とポイント
顧問税理士を選ぶ際は、単に価格や料金表だけでなく、費用対効果という視点が不可欠です。適正な顧問料を支払っても得られる価値が大きければ、事業の成長や安心につながります。
| 比較ポイント | チェック項目例 |
|---|---|
| サービス範囲 | 記帳・決算・税務申告だけでなく、経営相談や節税提案も含まれているか |
| コミュニケーション | 担当者と定期的に相談できる体制か、迅速なレスポンスがあるか |
| 専門性・実績 | 自社の業界に対する知見や、過去の対応事例は十分か |
| 追加料金の有無 | 税務調査・書類作成・面談など別途かかる費用を明確にしているか |
サービス内容ごとに料金を分解して比較し、自社に必要な対応が含まれるか、追加費用が明瞭かを事前に細かくチェックしましょう。複数の税理士から見積りを取り、料金や内容の違いを冷静に比較するのが賢い選び方です。
複数見積りと無料相談を活用した賢い顧問税理士の選び方
顧問税理士の相場や費用を適切に把握し、自社に最適なパートナーを選ぶためには、複数の税理士事務所に見積もりを依頼し、無料相談を賢く活用する方法がとても有効です。料金だけでなくサービス内容、対応範囲、経営アドバイスの有無などを比較検討することで、価格とサービスのバランスに優れた税理士を見極めることができます。
複数見積もりの取り方と見積もり内容のチェックポイント
顧問税理士へ依頼する際は、最低でも2~3社から見積もりを取得しましょう。見積もり依頼時には、法人・個人事業主の別、年商や従業員数、希望する業務範囲(記帳代行や申告対応など)を必ず伝えることが大切です。
見積もりで必ずチェックしたいポイントは下記のとおりです。
| チェックポイント | 内容例 |
|---|---|
| 月額顧問料 | 毎月の基本料金(具体的な金額) |
| 決算申告料、確定申告料 | 年1回の申告料・計算方法(法人・個人別) |
| 記帳代行・給与計算費用 | オプションサービスの有無と金額 |
| 範囲・回数 | 訪問頻度、オンライン対応、対応範囲 |
| 追加報酬・割増条件 | 範囲外業務や税務調査時の追加費用 |
条件が異なれば金額も大きく変わるため、記載内容の違いは必ず比較しましょう。「税理士顧問料5,000円」など格安料金に注目が集まりがちですが、何が含まれているかを確認しないと、後から追加料金が発生するケースもあるため注意が必要です。
無料相談の活用法と相談時に確認すべき重要ポイント
多くの税理士事務所では、法人・個人事業主を問わず無料相談を実施しています。この機会を活用し、「顧問税理士は何をしてくれるのか」「現状の課題に対応できるのか」など自社の疑問を率直に相談すると良いでしょう。
無料相談時に確認しておくべき主な項目は以下です。
- 会社の年商や従業員数に応じた顧問税理士の相場
- 実際のサービスの内容(税務相談・節税対策・記帳代行等)
- 決算や確定申告時の追加料金・発生条件
- サポートの範囲(税務調査立会い、経営支援等)の違い
- 事業経営や会計業務に関するアドバイスの有無
- オンライン対応や面談頻度
実際のやりとりでは顧問税理士が対応できる業務やサポート体制、契約内容の詳細を丁寧に確認し、不明点は遠慮せず質問しましょう。サジェストや「税理士はいらない?」など、顧問税理士が本当に必要か迷った場合でも、しっかりヒアリングしてもらえる事務所を選ぶのが、後悔しない選択につながります。
失敗しない税理士比較の3つの重要基準
複数見積もりや無料相談を通じて税理士を比較する際は、価格だけでなく下記の3つの重要基準に着目してください。
- 費用とサービス内容のバランス
- 月額顧問料や申告料が適正か、希望する業務内容が料金に含まれているか、将来的な追加費用の有無を必ず比較しましょう。
- 対応力と専門性
- 業界特有の会計知識や税務知識、経営アドバイスの経験があるか、質問への回答は的確かをチェックしてください。
- コミュニケーションの取りやすさ
- 税理士本人や担当者との相性、レスポンスの早さ、オンラインや訪問のしやすさなども長期的なパートナー選びには重要です。
この3点を軸に比較し、自社や自身に合った顧問税理士を選ぶことで、安心して経営や会計・税務を任せることができます。信頼性の高い事務所かどうか、過去の実績や紹介事例、顧客満足度などもあわせて参考にしてください。
顧問税理士の相場に関するよくある疑問解消Q&A集
顧問税理士の月額・年間費用の目安について
顧問税理士の費用は、会社規模や依頼内容によって大きく変わります。法人の場合、月額顧問料はおよそ20,000円〜50,000円が一般的と言われています。個人事業主の場合は10,000円〜30,000円が目安です。また、年間費用を計算する際は決算申告料も加算される点がポイントとなります。
費用の目安を分かりやすく比較します。
| 事業形態 | 月額顧問料の相場 | 決算申告料の相場 | 年間合計費用目安 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 20,000~50,000円 | 100,000~300,000円 | 340,000~900,000円前後 |
| 個人事業主 | 10,000~30,000円 | 50,000~150,000円 | 170,000~510,000円前後 |
この他にも選択するオプションや業種によって費用は増減します。
決算申告料や記帳代行料金の相場は?
決算申告料は法人で100,000円〜300,000円ほど、個人で50,000円〜150,000円が中心です。記帳代行料は依頼する仕訳数や作業ボリュームにより1,000仕訳までで10,000円程度から、件数が増えると30,000円以上かかるケースもあります。
記帳代行を依頼せず自社で処理できる場合は費用を抑えられますが、事務負担や会計ソフトの活用状況により外部委託のニーズも高まっています。税理士報酬の料金表を確認し、明細を比較することが大切です。
顧問税理士が不要なケースと導入のメリットとは?
最近は会計ソフトの進化や「Freeeを使えば税理士はいらない」といった声も聞かれます。しかし、下記のようなケースは税理士不要と考えられます。
- 小規模で帳簿処理が容易
- 決算や確定申告のみスポットで利用
- 簡単な青色申告
一方、顧問契約により、毎月の経理相談や節税アドバイス、税務調査時の対応といった専門性の高いサービスを受けられるのは大きなメリットです。会社の成長や規模拡大を見据えた経営判断にもつながります。
契約の種類やオプションサービスの料金体系の違い
顧問契約は「月次顧問+決算・申告」という基本パターンが主流ですが、下記のようなオプションが存在します。
- 給与計算、年末調整
- 資金繰りや融資相談
- 税務調査立会い
- 経営分析やレポート作成
これらは別料金となる場合が多く、事前に料金体系や契約範囲を確認することが重要です。依頼内容によるカスタマイズが可能な事務所も多いため、自社に必要なサービスだけを選択し、無駄なコストを避けるのがポイントです。
格安税理士と相場価格の税理士の違いはどこにあるのか?
格安をうたう税理士事務所は「月額5,000円」など非常に安い料金設定が目立ちますが、対応範囲が限定されていたり、面談や相談が有料オプションになるケースも珍しくありません。一方、相場価格の税理士は個別相談や迅速な対応など、サポート範囲・質ともに充実しているのが一般的です。
比較ポイントとして、
- 料金以外のサポート体制
- 税務調査・節税対策への対応力
- 経営相談や付加価値提供
を確認しましょう。コスト重視も良いですが、自社の事業規模や今後の成長計画を踏まえ、信頼できるパートナー選びが重要です。